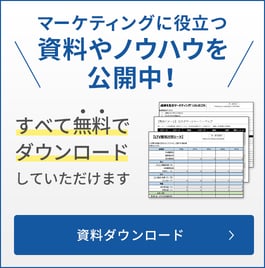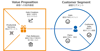%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%A8%E3%81%AF%3F%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%82%84%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%82%92%E8%A7%A3%E8%AA%AC.jpeg?width=4500&height=2830&name=%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB(DM)%E3%81%AE%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%A8%E3%81%AF%3F%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%82%84%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%83%BB%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E3%81%AE%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%82%92%E8%A7%A3%E8%AA%AC.jpeg)
ダイレクトメール(DM)は、企業が顧客に直接情報を届けられる有効なマーケティングの手段ですが、その効果を最大化するためには、効果検証が不可欠です。効果検証を行うことで、DM施策の良かった点、改善点、費用対効果を把握し、次の施策に活かすことができます。
今回のコラムでは、DMの効果検証に焦点を当て、その重要性や具体的な実施方法、そして実際の事例を解説します。
本コラムを通して、自社のDM施策の効果を最大限引き出すためのヒントを得ていただけると幸いです。なお、この記事のポイントは「【お役立ち資料】ダイレクトメール効果検証の設計」でまとめています。併せてご覧ください。
なぜDMには「効果検証」が必要なのか
DM は、企業が顧客に直接情報を届けられるダイレクトレスポンスメディア*です。また、その特性から一度だけ送付をして終わるのではなく、必ず効果検証をしてPDCAサイクルを回していくことが大切です。
*受け取り手に何かしらの行動(問い合わせ、Webサイト訪問など)を促し、その結果を計測することができるメディアのこと
DMの特性
DMには以下2つの特性があります。
- 個人宛に送付できる
DMは「個人」に届けられるので、自分宛の郵便物として開封されやすく、また「誰が」反応したのかを特定することが可能です - モノ(有形物)として届く
行動を喚起する仕掛け(特典など)を組み込みやすく、その特典が手元に残るため反応率の向上が期待できます。さらにはレスポンス結果も計測可能です。
DMにおけるPDCAサイクル
DMの特性を活かして、PDCAサイクルを回して施策の精度を高めていくことが重要です。
- 現状把握
自社顧客の現状を具体的に把握する - 計画
CRM戦略の設計、目標設定、ターゲットの絞り込み方や新たな切り口を検討する - 施策実行
課題解決の打ち手を設計し、実行する - 仮説を検証し、次の施策を練る

このようにDMは適切に設計しPDCAサイクルを回すことで、効果を高めていくことが期待できます。
DMの特性を理解し、効果的なDM戦略を構築しましょう。
効果検証の進め方
ここからはDMの効果検証の大まかな進め方を紹介していきます。
①目的にあわせた目標(KPI)の設定
企画の段階でそのDMで得たい効果を予測値として算出(仮説立て)し、KPIを設定します。
例えば、目的(最終的に達成したいこと)が「優良顧客のロイヤルティ向上」なのであれば、目標(目的達成のために到達すべき水準)は「優良顧客の売上比率の10%アップ」とするというようなイメージです。
KPIの設定は、DMの目的やターゲット層に合わせて適切に行いましょう。
②KPIと実際の施策の結果の比較
DM実施後の結果を算出し、設定したKPIと比較することで、成功要因、気づき、改善ポイントを洗い出します。
③結果を整理し次回施策につなげる
②で得られた結果を整理し、次回のDM施策に活かします。
成功要因を強化し、改善ポイントに沿った修正を行うことでより効果的なDM施策につなげていきます。
以上①から③を繰り返し行うことで、継続的に改善していくことができるのがDM施策の強みです。
効果測定用データを集めるときには「比較対象」が必要
前提として、効果検証を進めるためには施策の結果の測定(効果測定)を行う必要があります。
効果測定をするための仕掛けのひとつとして、比較するためのグループを作り、それぞれの条件でどのような効果が出たかを比較するA/Bテストがあります。
A/Bテストとは
施策対象者(ターゲットグループ)のうち、事前に「テストグループ」を抽出し、ターゲットグループとは異なる施策を実施することで、DMの効果を比較・測定する方法です。
例えばテストグループをふたつ設定し、それぞれにAパターン・BパターンのDMを送付すれば、どちらのDMがより効果的だったかのかを判断できます。
また、DMを送付しないテストグループを設定すれば、DMを送ること自体の効果を測定できます。
例:DM送付群とDM未送付群での効果測定
A/Bテストの注意点
A/Bテストで効果検証をする際には、セレクションバイアスに注意しなければなりません。
セレクションバイアスとは、比較するグループの属性に偏りがあると、テスト結果が歪んでしまうことです。
例えば、DM送付群に過去の高額購入顧客が多いと、DMの効果を過大評価してしまうことになりかねません。
制度の高い効果測定を行うためには、無作為なグループ分けで偏りを防ぎ、比較グループ間の属性を均等にすることが重要になります。
セレクションバイアスについては下記のコラムで詳しく説明しています。
効果測定用データを集める手法例
次に効果測定用データを集める具体的な方法を3つ紹介していきます。
①二次元コードでのアクセス解析
二次元コードは、BtoB向け、BtoC向けともに現在では主流な方法のひとつと言えます。
DMに二次元コードを載せて、ウェブサイトへのアクセスを誘導し、遷移した数値を計測します。
例えば、二次元コードのURLにパラメータ*をつけ、DMからのサイト流入なのかを判別したり、すべてのDMに個別の二次元コードを記載し、誰がアクセスしたかを判別することが可能です。
*パラメータ:アクセス元を特定するためにURLの末尾に付加する文字列のこと
②ハガキ・申込書などのレスポンスツールの同封
DMに返信用ハガキ、申込書、来店クーポンなどのレスポンスツールを同封し、その返信率や使用率を測定・分析します。
アナログな回収方法であるため、デジタルツールでリアクションを得にくい層向けの製品やサービスに適した方法と言えます。
③アウトバウンドコールへの連携
DMを送付した顧客に対して架電を行います。
DMの内容に対する反応や意見、商品・サービスに対する興味関心などの定性情報はもちろん、顧客の属性情報(年齢、性別、職業など)やDMを開封したか、同封した特典を使用したかなどの定量情報も得ることができます。
また、BtoB向けサービスの新規顧客獲得の際にもよく使われる方法です。
DMの効果検証の事例
ここからは実際にフュージョンがご支援したBtoB向けとBtoC向けの効果検証の事例を、それぞれ一つずつ紹介していきます。
どちらの事例もDMの特性を活かし、KPI設定から効果検証を行い施策の継続につなげています。
①freee株式会社様(BtoB)
freee株式会社は、企業や個人事業主向けに、バックオフィスの業務効率化するためのクラウドサービス「freee」を提供しています。
この施策では上場企業の経理部全員へ「freee」の認知と導入推進のために、テンキー型のチョコレートを同梱したDMを送付しました。 この事例では、効果測定用データを集める手法として「アウトバウンドコールへの連携」を採用しています。
この事例では、効果測定用データを集める手法として「アウトバウンドコールへの連携」を採用しています。
架電時のDMの認知率は50%超と非常に高い結果となり、「チョコを送りました」というフレーズが強力なフックとなりスムーズに商談につなげていくことができました。
事例の内容
- KPI設定・施策内容
アウトバウンドコールへの連携を意識したクリエイティブの作成
箱型のDMに経理部門に馴染みの深いテンキー型のチョコレートを入れることにより、架電時に会話をしやすいDMを作成 - 効果測定・検証
通常のアウトバウンドコールに比べ受付突破率*は5倍以上
DM到着のタイミングで、送付した全企業へ架電
DMの認知をきっかけに、資料送付の要否、責任者名・連絡先の収集、現在の決算業務の課題などをヒアリング
*担当者や決裁者と話すことができた割合 - 次回施策への活用
アウトバウンドコールで得た情報をもとに、施策を改善しながら継続して施策を実施した
②株式会社いなげや様(BtoC)
株式会社いなげやは、首都圏で食品スーパーマーケットを運営しています。
日頃からいなげやを利用している会員に向けて、おせちの案内を初めてDMで実施した事例です。
おせちのお重をDMのデザインに落とし込み、おせちの疑似体験から販売促進を狙いました。
当初想定していたターゲットである40〜50代だけでなく、60〜70代の購入も多く新たなマーケティング施策への気づきにもつながりました。
事例の内容
- KPI設定・施策内容
購買データの分析から、おせちは商材としてDMとの相性が良いという仮説を立てた
販促計画からKPIを設定 - 効果測定・検証
2,700通のDM送付を行い、ROI* 24.3%の結果となる
レスポンス率 14%の高い効果が得られ、測定・検証の結果、通数を大幅に増加して再度施策を行うことに決定
*DM施策に投資した費用に対して、どれだけの利益が得られたかを示す指標 - 次回施策への活用
2,700→15,000に通数を拡大し、ROIも25.3%に増加
DMで展開したおせちの売上前年比は約130%に
DMの特性を活かして効果検証の設計を行いましょう
DMは、顧客に直接情報を届けられる有効な手段ですが、送って終わりではDMの特性を最大限活かしているとは言えません。
上記2事例からわかるように、DMは「なんとなく」送付をするのではなく、戦略的に効果測定・検証を行いPDCAサイクルを回すことでより一層施策の効果を高めることができます。
今回のコラムの内容は下記の資料にまとめています。
ご興味のある方は下記よりダウンロードしていただき、DMの効果検証の設計の参考にしてください。
フュージョン株式会社は、CRM戦略策定からDMを含めた個別施策の企画・制作、実施後の効果検証までをワンストップで支援しています。初めてDMの実施を検討している場合や、現在のDM施策の効果に課題をお持ちの場合は、ぜひ一度フュージョン株式会社へお問い合わせください。