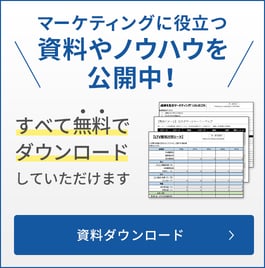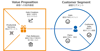現代のマーケティングにおいて、膨大なデータを収集するだけでは不十分です。重要なのは、収集したデータから的確な示唆を導き出し、それをもとに戦略を立案・実行し、成果を継続的に改善していくことです。マーケティングのPDCAサイクルの基本であり、その中で注目されているのがBIツール活用です。
現代のマーケティングにおいて、膨大なデータを収集するだけでは不十分です。重要なのは、収集したデータから的確な示唆を導き出し、それをもとに戦略を立案・実行し、成果を継続的に改善していくことです。マーケティングのPDCAサイクルの基本であり、その中で注目されているのがBIツール活用です。
本記事では、BIツール活用のメリットを具体例とともに詳しく解説します。
BI化で得られるメリット
マーケティング施策の成功には、データに基づいた意思決定が欠かせません。しかし、膨大なデータを扱う中で「どのデータを見ればいいのか分からない」「分析に時間がかかりすぎる」といった課題に直面することも多いのではないでしょうか。
そこで役立つのがBI(ビジネスインテリジェンス)ツールです。BI化によって得られるメリットは大きく分けて3つあります。
- 考察・リサーチの緻密化
- KPIマネジメントの最適化
- 業務フローの省力化
 各メリットについて詳しく解説します。
各メリットについて詳しく解説します。
BI化で得られるメリット①考察・リサーチの緻密化
BI化によって得られるメリットの1つが、「考察・リサーチの緻密化」です。従来のデータ分析では、異なるファイルに掲載されているデータを手作業でまとめるのに多くの時間と労力がかかっていました。
その結果、リサーチの精度が上がらず、考察が浅いものとなるケースがあります。より高い精度で考察するためには、必要なデータを素早く収集し、的確に分析することを補助するツールが必要です。
BIツールは、売上データ、顧客の反応、Webサイトのトラフィック、SNSのエンゲージメントといった複数のデータソースからリアルタイムで情報を収集し、1つのダッシュボード上で統合して表示できます。担当者は分析に必要な数字を簡単に確認しながら、さまざまな角度からデータを探索的に分析できるようになります。
(ダッシュボードイメージ画像) さらに、BIツールは既存の仮説を検証するうえでも役立ちます。例えば、「特定の地域でのキャンペーンが売上に大きな影響を与えた」といった仮説がある場合、地域別の売上推移、顧客層の変化、広告のクリック率などを簡単に可視化し、データに基づいて素早く仮説を確認できます。
さらに、BIツールは既存の仮説を検証するうえでも役立ちます。例えば、「特定の地域でのキャンペーンが売上に大きな影響を与えた」といった仮説がある場合、地域別の売上推移、顧客層の変化、広告のクリック率などを簡単に可視化し、データに基づいて素早く仮説を確認できます。
加えて、BIツールは考察結果を即座に可視化できるのも大きな特徴です。棒グラフ、円グラフ、ヒートマップなどでデータを可視化することで、複雑な数値情報も直感的に理解しやすくなります。例えば、広告のクリック率と売上の相関関係を視覚化すれば、どの施策が最も効果的であったかを一目で把握できます。
BI化で得られるメリット②KPIマネジメント最適化
BI化によって得られるもう1つのメリットが「KPIマネジメントの最適化」です。マーケティング戦略の成功は、KPI(重要業績評価指標)の適切な設定と継続的なモニタリングにあります。
BIツールの導入により、KPIの進捗を可視化し、全社共通認識を醸成することが可能です。
KPIツリーの構造を活用することで、目標達成のために重要な施策や、その施策が必要な理由を論理的に説明できるようになります。単なる数値の羅列ではなく、目標と施策の因果関係が明確化され、チーム全体で共通認識を持つことが可能となります。
弊社、フュージョン株式会社のKPIマネジメント支援事例を紹介します。
| クライアントのミッション | ・店舗会員向けCRM戦略の立案と実行 ・全社のマーケティング方針策定および各店舗への発信 |
| 課題 | ・従来のマーケティング戦略では、達成目標内容に定性的な側面が強く、組織としてPDCAを回しながら再現性を持たせたマーケティングが行えていなかった。 ・マーケティング戦略策定プロセスが属人的な技能・ノウハウに依存しており、組織内で形式知化されていなかった。 |
| 成果 | 全社一丸でのマーケティング活動を、再現性を持って実施するための仕組み化が大きく前進した。 |
| 具体的な成果物 | ・店舗アプリデータ分析レポート ・KPIツリー |
A社のマーケティング部は、全社規模での年度および月度のマーケティング戦略やマスタープランの策定、それを全社に発信するという重要な役割を担っていました。これまでの取り組みは主に定性的なアプローチに偏っており、目標達成の基準となるKPIの体系化や、その進捗を管理するための明確なフレームワークが存在していませんでした。
その結果、各施策は個別のアイデアや経験則に依存することが多く、再現性のあるマーケティング活動を継続的に実施することが難しい状況に陥っていました。
そこで弊社は、A社に対してBIツールを活用したKPIマネジメントの仕組み化を支援しました。まず、A社の課題を明確にするために、店舗アプリのデータを分析し、その結果に基づいてKPIを整理しました。その結果、店舗アプリ自体のKPIと経営上のKPIをうまく連携させられていないために、事業部と現場が一体となって目標に向かえる状態ではないことが発覚しました。
そこで、A社のこれまでの経緯や実現可能性も考慮し、分析設計~分析実施・示唆出しおよびKPIツリーの再構築を実施。その結果、A社は全社一丸となったマーケティング活動を再現性のある形で実施するための基盤構築に成功しました。
本事例の詳細につきましては、こちらの記事をご覧ください。
BI化で得られるメリット③業務フローの省力化
BI化により、「業務フローの省力化」が可能です。エクセルを用いたデータ管理や分析は、膨大なデータを扱う際に作業負担が増大し、手動によるミスも発生しやすいという課題があります。
複数のデータソースから情報を集約し、数式を設定してグラフを作成するプロセスは非常に時間がかかり、更新のたびに手作業で修正する必要がありました。
BIツールを導入することで、データの取り込みから集計、分析、可視化までをワンクリックで自動処理できるため、担当者は複雑な操作や手動更新の手間から解放されます。
業務フローの自動化による効果やBIツールの基本については、こちらをご覧ください。
BI化・自社データ活用の分類・パターン
 BIダッシュボードのタイプは、企業がどの視点でデータを分析したいかによって大きく4つに分類されます。
BIダッシュボードのタイプは、企業がどの視点でデータを分析したいかによって大きく4つに分類されます。
A「基本構造リサーチ系」は、売上や顧客構成などの基礎的なデータを可視化することで、ビジネスの全体像や課題の本質を把握することが目的です。たとえば、売上推移の分析や顧客セグメントごとの傾向把握に活用できます。
B「好不調チェック系」は、業績の好不調を迅速にキャッチするためのもので、異常値や予想外の変動を早期発見し、問題発生時の迅速な対応を可能にします。売上急減のアラートを出すほか、不良品率の上昇などをリアルタイムで確認できます。
C「施策効果レビュー系」は、マーケティング施策やプロモーションの効果を定量的に評価することです。施策ごとの投資対効果(ROI)やコンバージョン率などを分析し、次の施策立案に役立てることができます。
D「異常検知アラート系」は、通常のパターンから逸脱した動きを自動的に検知して警告を発するものです。重大な問題が発生する前に予兆をつかみ、対策できるようになります。
重要なのは、単にダッシュボードを作成することが目的化しないよう、自社にとって本当に必要なタイプを見極めて設計することです。 BIツールを導入しても、どのデータを何の目的で可視化したいのかが定まっていないと、ダッシュボードを構築しても実務では利用されないおそれがあります。
さらに、タイプに業種特有の慣習や商品特性を組み合わせることで、より実践的で効果的な分析が可能となります。企業内で実績として積み重ねた実績や引き継がれている情報、担当者の長年の勘も含めて、着目すべき項目を改めて精査することで、自社独自の価値あるダッシュボードが完成します。
BIツールを自社に適した形で導入することが重要
BIツールは、使う目的や分析の重点ポイントを明確にせずに導入・設計を進めてしまうと、形骸化するリスクがあります。
フュージョン株式会社は、システムベンダーではなく、CRM領域に強みを持つマーケティング支援会社です。だからこそ、業界ごとの特性や課題をヒアリングした上で、当社独自の運用実績を活かし、BIツールを“使うこと”そのものが目的にならないよう、本当に成果に結びつくダッシュボード設計を支援できます。特に、TableauをはじめとしたBIツールの運用実績が豊富で、小売・通販・卸など、さまざまな業界での成功事例がございます。
私たちの強みは、CRM戦略に基づくKPI設計から、実際のマーケティング施策の企画・実行までを一気通貫でサポートできることです。単なる数字の可視化だけでなく、その数字が示す意味や次に取るべきアクションまで見据えて支援いたします。
BIツールの導入・設計・運用に課題を感じている場合は、ぜひフュージョン株式会社にご相談ください。